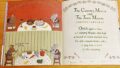生まれも育ちも奈良県で、明日香と万葉集が好きなみくるです。
こちらの記事では、かつては推古天皇の小墾田宮(おはりだのみや)と推定されていた古宮遺跡をご紹介しました。
小墾田宮については、昭和62年(1987年)に、雷丘東方遺跡で、奈良時代の井戸から「小治田宮」と墨書きされ土器が多数出土したことから、少なくとも奈良~平安時代の小治田宮については、雷丘東方遺跡であることが判明しました。
これらの成果から、推古天皇の小墾田宮も雷丘周辺にあったと考えられるようになりました。
【飛鳥時代の始まりの地】明日香村豊浦【古宮遺跡(古宮土壇)】 | みくるの森 (mikurunurie.com)
今回は、推古天皇の小墾田宮があったと考えられる雷丘周辺と、柿本人麻呂の万葉歌碑をご紹介します。

雷丘と柿本人麻呂の万葉歌碑
雷神をとらえたという伝説の丘「雷丘」
古宮遺跡より東へ行くと飛鳥川が見えて来ます。
写真左手に見えるこんもりとした丘が雷丘(いかづちのおか)です。

高さ10mの小さな丘です。
階段を付けて整備されていて上に登ることができます。
登っても見晴らしが良い訳ではなく、特になにも無いそうです。

説明板に柿本人麻呂の歌が書かれています。

日本書紀や日本霊異記に、雷神の降臨する説話を伝える聖なる丘であったことが記されており雷丘の名もこれに由来しているらしい。
雷丘の説明板より
『日本書紀』の雄略天皇の巻に次のようにあります。
雄略天皇が、家臣の小子部栖軽(ちいこさべのすがる)に「私は三諸岳(みもろやま)の神の姿が見たい。お前は力が強いので捕まえてこい。」と命じます。
栖軽が三諸岳で大蛇を捕らえて天皇に見せたところ、その蛇は雷のような音を轟かせながら目を爛々と光らせたので、天皇は恐れてご覧にならず、蛇を丘に放させました。そして、その丘に雷(いかづち)という名を与えました。
ぶらり日本書紀/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)
また、『日本霊異記』には
栖軽が亡くなった後、雷が落ちた場所に彼の墓をつくり、「雷を捕まえた栖軽の墓」と碑を建てました。すると雷は怒ってその碑を蹴り割ろうとしたところ、柱が割けたところに足が挟まって抜けなくなりました。そして天皇は、「生きても死んでも雷を捕まえた栖軽の墓」と碑を建てなおしました。これが雷丘のはじまりといわれています。
ぶらり日本書紀/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)
とあります。
このように、雷丘は古代の人にとっては神話の舞台になった聖なる丘でした。
古代の人に最も恐れられていた自然現象は「厳つ霊(いかつち)」、つまり「神鳴り(かみなり)」でした。
雷の多い場所だったので、このような伝承が生まれたのだと思われます。
柿本人麻呂の天皇を讃える万葉歌
雷丘の北側が広場になっていて、柿本人麻呂の万葉歌碑が建っています。

(原文)
皇者 神二四座者 天雲之
雷之上尓 廬為流鴨

(題詞)
天皇の雷岳に御遊しし時に、柿本朝臣人麿の作れる歌一首
(書き下し)
大君は 神にしませば 天雲の
雷の上に 廬らせるかも
万葉集 巻3-235 柿本人麻呂
揮毫 犬養孝
(訳文)
大君は神でいらっしゃるので、遥かな天雲の中に轟く雷のさらにその上に仮宿りをなさっておいでのことだ。
天皇を神格化し、雷神をも従えておられるわが大君よ、と讃えています。
万葉集巻三の冒頭におかれた非常に有名な一首です。この大君とは天武天皇か、もしくは次の代の持統天皇のことだといわれています。
ここが神話や万葉集に登場し、天皇が行幸された場所かと思うとワクワクしました。
この歌碑は犬養孝先生が揮毫された明日香村内にある万葉歌碑15基のうちの一つです。
「雷丘東方遺跡」推古天皇の小墾田宮推定地
柿本人麻呂の歌碑がある広場の東の一帯には、飛鳥時代(592~710年)のお寺や宮殿がつくられました。

雷丘の東の一帯は、奈良時代の離宮のひとつである小治田宮の跡と考えられ、推古天皇の小墾田宮(603~628年)もこの近くにあった可能性が高くなっています。

北を見ると天香久山が見えます。

西を見ると飛鳥川と畝傍山が見えます。
蘇我氏の庭園跡と考えられている古宮遺跡は飛鳥川の向こう側にあります。

雷丘のアクセス
奈良県高市郡明日香村雷138
お車をご利用の場合
雷交差点すぐ。
駐車場はありません。
「豊浦駐車場」に停めて歩かれると便利です(徒歩7分)。
※有料(普通車500円)です。

公共交通機関をご利用の場合
近鉄橿原神宮前駅から奈良交通バス(かめバス)
飛鳥下車 徒歩6分
豊浦駐車場下車 徒歩7分

おすすめの本
奈良万葉の旅百首 奈良まほろばソムリエの会 著 上野誠 監修
京阪奈情報教育出版(2021/2/28)
万葉の奈良を歩くためのガイドブックです。
周辺の地図や歌碑が紹介されたり、現地を訪ねるために掲載された情報がとてもきめ細やかで、興味深い写真なども盛り込まれています。
万葉集にこだわらなくても、奈良県内の散策を多角的に楽しめるガイドブックになっています。
この本を読まなければ知らなった場所も多くありました。
持ち歩きに便利な新書サイズなので、本を片手に奈良万葉の世界に触れています。
今回の記事でも参考にさせて頂きました。
明日香村の万葉歌碑を歩く
今回ご紹介した歌碑は「犬養万葉記念館」で頂いた『明日香村の万葉歌碑を歩く』の2番目に掲載されています。
掲載されている歌碑40基をまとめてご紹介しています。
最後までお読み頂きありがとうございます。