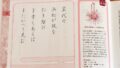『万葉集』と『百人一首』が好きで、歌碑巡りも楽しんでいるみくるです。
花や草木に詳しくなれると、もっと和歌を楽しめそうと思い始めたのが『なぞりがき万葉集』です。

『なぞりがき万葉集』は、現存する日本最古の歌集『万葉集』全20巻、約4500首の中から、萩や梅、撫子など、花や草木を詠んだ歌を選んで取り上げられた本です。
花や草木に思いを託して歌を詠んだ当時の人たちの心に触れ、『万葉集』の世界を味わいながら、ゆったりと美文字レッスンの時間を楽しんでいます。
今回は、春の植物より「サクラ」を詠んだ歌をご紹介します。花の盛りが短い桜をなごり惜しむ気持ちを詠んだ山部赤人の歌です。
「サクラ」を詠んだ山部赤人の歌
あしひきの山桜花日並べて…
『なぞりがき万葉集』では、植物を四季で分類して、現代植物名の五十音順に掲載されています。

(原文)
足比奇乃 山桜花 日並
而如是開有者 甚戀目夜裳
(読み下し)
あしひきの 山桜花 日並べて
かくし咲けば はだ恋ひめやも
万葉集 巻8-1425 山部赤人
(現代語訳)
(あしひきの)山の桜の花が、何日も何日もこのように咲くのなら、どうしてひどく恋しく思うだろう。
(語義)
あしひきの:「山」にかかる枕詞
山桜花:山に咲く桜の花。
日並べて:何日も続けて
恋ひめやも:「恋ひめやも」の「や」は、反語。「も」は、詠嘆。どうしてこんなにひどく恋しく思うだろうか、いや、こんなに恋しく思うことはないだろう。
この歌のポイントは、「散るからこそ美しい」という日本の美意識が表現されている点にあります。桜はすぐに散ってしまうからこそ、その一瞬の美しさが際立ち、人々は強く惹かれ、そして散った後もその余韻を恋しく思うのです。
この歌は、散る桜に永遠の美しさや儚さを重ね合わせ、人生や恋の切なさをも詠んだ、非常に奥深い一首と言えるでしょう。
歌聖と称えられた旅の歌人:山部赤人
「旅の歌人」として知られる山部赤人は、奈良時代に活躍した『万葉集』を代表する歌人です。柿本人麻呂と並び称され、「歌聖」と呼ばれるほどの卓越した才能を持っていました。
彼の歌は、旅先で出会った雄大な自然の情景を、まるで絵画のように鮮やかに描き出す「叙景歌」に優れています。感情を直接的に語るのではなく、美しい景色を通してその心情を深く感じさせるのが彼の特徴です。
こちらは、『百人一首』4番に収載されている歌です。
田子の浦ゆ うち出でて見れば 真白にぞ
富士の高嶺に 雪は降りける
幽玄を主題に置いた『新古今集』の中から取られた一首です。
旅の途中で田子の浦から富士山を眺めた時の歌です。雪をいただき、白く輝く富士山の雄大な姿を、簡潔でありながら力強く詠み上げています。この歌は、彼の優れた叙景能力を最もよく示す作品として知られています。
これらの歌が示すように、山部赤人は自然の情景に深く心を寄せ、その美しさを永遠のものとして歌に残しました。彼の歌は、現代を生きる私たちにも、日本の原風景の美しさや、儚さの中にある真の価値を教えてくれます。
実はこの歌は、最初に収載された『万葉集』では
田子の浦ゆ うち出でてみれば 真白にそ
富士の高嶺に 雪は降りける
となっています。
「白妙の」は布の白さにたとえた表現ですが、こちらは「真白にそ」となっていて、より直接的な言い方になっています。
最後の「ける」も「降ってるなあ」というような、今初めて気が付いた感動を示す表現になっていて、百人一首の歌よりずっと素朴であることが分かるでしょう。
一方、『新古今集』バージョンは表現がずっと繊細で、「降りつつ」のように時間の流れが消えたような幻想的な情景となっています。男ぶり、素朴さの万葉集と、都会的で幽玄、繊細な新古今集の違いを考えるのにいい一首だといえます。
『なぞりがき百人一首』でも、なぞりがきと和歌を楽しんでいます。
万葉集の桜は「散らない」!? 知られざる日本人の美意識のルーツ
山部赤人の「あしひきの山桜花~」の歌は、散る桜の美しさ、そしてその儚さに心を重ねる日本人の美意識を象徴する一首として知られています。しかし、実はこの感覚は、必ずしも当時の人々の一般的な感覚ではなかったかもしれません。
『万葉集』を紐解くと、現代の私たちが持つ「桜は儚く散るもの」というイメージとは真逆の歌が多数見つかります。桜を詠んだ歌の中には、「散らないでくれ」「いつまでも咲き続けてほしい」と願うものが多く、散りゆく桜を惜しむ歌はほとんど見られません。
なぜなら、当時の人々にとって桜は単なる美しい花ではなかったからです。桜は、春の到来を告げ、その年の豊作を占う「稲の神が宿る神聖な木」でした。神聖な花が散ることは、不吉なことと捉えられていたのです。
つまり、山部赤人の歌は、多くの人が桜に抱いていた「永遠であれ」という願いとは少し異なる、「散るからこそ恋しい」という特別な感情を詠んだ、革新的な一首だったのかもしれません。この歌は、後世の武士や文人たちが桜に「潔さ」や「儚さ」を見出す、その美意識の夜明けを告げたとも言えるでしょう。
私たちは、桜の『儚く散る美しさ』に惹かれます。しかし、それは長い歴史の中で形作られた価値観だったのです。こうして見ると、私たちが愛する桜の姿は、単なる自然の現象ではなく、時代や文化によって変化してきた「日本人の心そのもの」だと言えるのではないでしょうか。
『万葉集』の時代のサクラ
『万葉集』の時代は、サクラといえば山地に自生する日本固有種の「ヤマザクラ」を指していました。
ヤマザクラは、赤みを帯びた若葉と白い花が同時につくのが特徴で、ソメイヨシノの魅力とは違う、繊細な花のたたずまいが印象的です。
奈良県の吉野山は山桜の名所として知られます。

奈良県橿原市に咲く桜です。ソメイヨシノと並べて、吉野山の山桜が植えられています。

なお、ソメイヨシノは江戸時代につくられた品種です。
現代の桜の美しさと、万葉集の力強い桜。あなたはどちらに魅力を感じますか?
使用したなぞり書きの本
ぞりがき万葉集―いにしえの草花の歌 ユーキャン学び出版(2022/10/21)
本の内容はこちらの記事で詳しくご紹介しています。
使用したガラスペンとインク
エルバンさんの「アンティークブーケ」のインクでなぞりました。

ガラスペンはまつぼっくりさんの「雲母ピンク細字」です。
この組み合わせで使って写真を撮るのが好きです。
エルバン トラディショナルインク アンティークブーケ
ガラス工房 まつぼっくり ガラスペン
ガラスペンで愉しむなぞり書き
なぞり書きのまとめページを作っています。
流行りのガラスペンとインクを使いたいけれど、文字を書く習慣が無いし何に使ったらいいか分からないって思っていた私にとって、なぞり書きはぴったりなガラスペンとインクの楽しみ方です。
書写とは違い、なぞり書きはなぞることに集中できるのが気に入っています。
ガラスペンの他に万年筆やボールペンなどでもなぞり書きを愉しんでいます。
最後までお読み頂きありがとうございます。