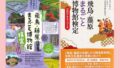山の辺の道や古墳が好きで、奈良県天理市によくでかけているみくるです。
「天理市」と聞くと、天理教の街という印象を持つ方も多いかもしれません。たしかに、整然とした街並みや天理教教会本部の姿は、このまちを象徴する風景のひとつです。
けれども天理の魅力は、それだけではありません。
春にはやわらかな花びらが舞う桜並木、秋には黄金色に染まるイチョウ並木。
季節の彩りがまちを包み、訪れる人をやさしく迎えてくれます。

さらに、市内には日本最古の神社・石上神宮や、古墳時代の面影を今に伝える杣之内古墳群、人々の信仰と暮らしをつないできた山の辺の道など、古代からの歴史と自然が息づいています。
天理駅前のランドマーク「コフフン(CoFuFun)」を出発点に歩けば、宗教と歴史、そして四季の風景が調和する“もうひとつの天理”に出会えるはずです。
天理市の玄関口|天理駅と駅前広場ココフン
「天理総合駅」天理臨に対応する広大なターミナル駅
天理駅は、JR桜井線(万葉まほろば線)と近鉄天理線が乗り入れる接続駅です。

この駅が「天理総合駅」と呼ばれるのは、元々別々だった両社の駅が1965年(昭和40年)の国鉄線高架化に伴い、一つの駅舎に統合された歴史を持つからです。
JRの駅が高架、近鉄の駅が地上という異なる構造を持つ珍しいターミナル駅であると共に、ホームや駅前ロータリーが非常に広大に作られています。
これは、天理教の祭典時に全国から信者を受け入れる「天理臨(てんりりん)」と呼ばれる臨時列車に対応するためです。
長年にわたり、信仰と鉄道の歩みをつないできた「天理臨」は、天理の歴史を今に伝える特別な存在といえるでしょう。
古墳がテーマの広場「コフフン(CoFuFun)」
駅のすぐ前に広がるのは、個性的なデザインの公共空間「天理駅前広場 コフフン(CoFuFun)」です。

大小連なる白い屋根は、天理市周辺に数多く存在する古墳(こふん)をモチーフにデザインされました。

「CoFuFun」という名前は、古墳と、楽しさの「フフン」、そして共同体(Co)と楽しむ(Fun)という言葉から生まれています。

ここでは、子供たちが遊べる遊具やカフェ、屋根付きの休憩スペースが一体化しており、市民や観光客の憩いと交流の場として親しまれています。

天理教教会本部がある宗教都市・天理の風景
天理駅と天理教教会本部を繋ぐ、都市計画の壮大さ
天理駅前からは、天理教教会本部へ向かって道がまっすぐ東に伸びています。

天理市を訪れると、まず目に入るのは天理教教会本部を中心とした整然とした街並みです。
信者の方々の黒いはっぴ姿や、広々とした参道は、この街ならではの景観で、天理が「宗教都市」として知られる理由を感じさせてくれます。
天理教教会本部を中心に広がるのが、「おやさとやかた構想」です。
この構想は、教祖・中山みきのお言葉に基づき、信仰と暮らしを一体化させた都市づくりを目指したもの。

駅から徒歩で歩くと、天理教教会本部を囲むように、学校や医療施設、信者の宿泊所などが整然と並び、信仰・教育・日常生活が調和する街の姿を見ることができます。

建物の屋根の形や統一感のある配色など、景観の美しさも特徴の一つで、ただの宗教施設ではなく、街全体がひとつの「モデル都市」のような印象を与えます。

散策しながら眺めることで、天理の街が信仰に根ざしながらも、暮らしと文化の場として息づいていることを実感できるでしょう。
天理大学附属天理参考館
天理大学附属天理参考館は、奈良県天理市にある「世界の生活文化と考古美術の博物館」です。

考古・美術工芸・歴史・民俗など、世界各地から集められた約30万点もの資料を収蔵し、常設展では日本や世界の多様な文化に触れることができます。

企画展や特別展も定期的に開催されており、訪れるたびに新しい発見があるのが魅力です。
こちらの記事では、「天理大学附属天理参考館」で開催された第99回企画展「こけしⅡ―遠刈田と土湯・中ノ沢―」の様子をご紹介しています。
宗教的景観のハイライト「天理教教会本部」
参道を歩ききると、おやさとやかたの中心、天理教教会本部に至ります。

天理教教会本部は日本国内に約1万6千あると言われる天理教教会の本部です。
天理教教会本部は親神(おやがみ)・天理王命(てんりおうのみこと)によって人間創造の地点とされている聖地「ぢば(地場)」があり、日本国内にある天理教の教会は聖地「ぢば」の方角を向いて建てられています。

天理教教会本部では聖地「ぢば」を中心に総桧造の神殿と四方(東西南北)を取り囲むように「かんろだい(甘露台)」を芯に礼拝場が建てられています。
また神殿北側に教祖殿・祖霊殿も建てられ、約800メートルの長い回廊で繋がれています。神殿と四つの礼拝場は合わせて3,157畳の広さがあります。

どなたでも自由にご参拝いただけるよう、本部神殿は365日24時間開かれています(夜間は南礼拝場からご参拝ください)。
拝観料、事前申し込みは不要です。
ぜひ神殿に上がられて、天理教の聖地「ぢば(地場)」を体感されて下さい。天理教の公式サイトで、参拝の仕方を確認できます。
古代史のロマン|古墳と山の辺の道
もう一つの天理市の顔は、古代日本の歴史を雄弁に物語る壮大な古墳と山の辺の道です。
古代ロマンの道「山の辺の道」
天理市は、日本最古の道の一つと言われる「山の辺の道」の北部に位置しています。

大和の国の東側、山裾を縫うように続くこの道は、古代の天皇陵や有力者の墓、そして神社仏閣を結んでおり、美しい里山の風景を楽しみながら歴史散策ができる人気のウォーキングコースです。

こちらの記事では、「内山永久寺跡(うちやまえいきゅうじあと)」をご紹介しています。桜の頃はベストショットの場所として知られ、その美しい写真は、観光パンフレット「山の辺の道」の表紙になっています。
天理の代名詞!必見の巨大古墳群
天理市内には、箸墓古墳に後続するとされる大和古墳群や柳本古墳群が広がり、日本最大級の巨大古墳が点在しています。
行燈山(あんどんやま)古墳
宮内庁により崇神天皇陵に治定されている、全長約242mを誇る巨大前方後円墳です。

渋谷向山(しぶたにむかいやま)古墳
宮内庁により景行天皇陵に治定されている、全長約300mの国内最大級の古墳の一つです。

こちらの記事では、景行天皇陵(渋谷向山古墳)について詳しくご紹介しています。
黒塚(くろづか)古墳
大量の三角縁神獣鏡が出土し、邪馬台国畿内説の重要な証拠となったことで有名な古墳です。

隣接する「黒塚古墳展示館」で竪穴式石室が実物大で再現されています。

日本最古級の神社「石上神宮(いそのかみじんぐう)」
山の辺の道沿いには、日本書紀にも登場する、国内でも有数の古い歴史を持つ石上神宮があります。

古代の有力豪族・物部氏の総氏神であり、神庫には国宝の「七支刀(しちしとう)」が保管されています。

境内には、ニワトリが放し飼いにされている珍しい光景も見られます。

こちらの記事では、石上神宮の見どころをまとめてご紹介しています。
季節の彩り(四季の景観)
歴史と信仰の街である天理は、季節ごとに美しい景観を見せてくれます。
天理の秋の風物詩:イチョウ並木
天理市の秋の主役といえば、やはり「親里大路(おやさと大路)のイチョウ並木」です。天理市役所付近から天理大学へと続く約600メートルの並木道には、約100本のイチョウが植えられています。

見頃になると、道路全体が鮮やかな黄金色に染まり、まるで金色のトンネルの中を歩いているよう。

特に見応えがあるのが、天理教のシンボル的な建築物「おやさとやかた」とのコントラストです。

こちらの記事では、親里大路のイチョウ並木や、天理市教教会本部の紅葉の様子などをご紹介しています。
春を彩る桜並木
天理教教会本部の南側一帯では、約40年前から、全国各地からお供えされた桜の苗木が川岸に少しずつ植えられてきました。現在では、大きく成長した桜が3月下旬から一斉に開花します。

ソメイヨシノ、ベニシダレザクラ、陽光ザクラなど5種類があり、白色から濃いピンクまで、さまざまな色の桜が少しずつ時期をずらして咲くので、長期間にわたって色の変化を楽しむことができます。

こちらの記事では、『万葉集』にも詠まれた布留川と、河川敷の桜並木をご紹介しています。
天理教教会本部の境内には、全国の信者さんから献納されたさまざまな品種の桜が植樹されています。中でもひときわ目を引くのは、別席場前広場に咲く3本の枝垂れ桜(シダレサクラ)です。

こちらの記事では、天理市を象徴する天理教教会本部の枝垂れ桜と、境内に咲く様々な品種の桜ををご紹介しています。
まとめ:二つの顔のコントラスト
天理市は、駅前のコフフンから一歩踏み出すだけで、壮大な宗教都市としての近代の顔と、巨大古墳が語りかける古代日本の起源の顔という、極めて対照的で深い歴史に触れることができる場所です。
天理駅前の「コフフン」をスタート地点に、ぜひこの二つの顔を持つ天理の魅力を、ご自身の足で辿ってみてはいかがでしょうか。
天理駅へのアクセス
住所:奈良県天理市川原城町816
天理市を訪れる際の玄関口となる天理駅への主要なアクセス方法は以下の通りです。
| 出発地 | 路 線 | 所要時間の目安 | 備 考 |
| 近鉄 奈良駅 | 近鉄奈良線 → 大和西大寺駅 → 近鉄橿原線 (平端駅乗換) → 近鉄天理線 | 約40分〜50分 | 平端駅での乗り換えが必要です。 |
| 近鉄 京都駅 | 近鉄京都線 (平端駅乗換) → 近鉄天理線 | 約1時間10分 | 特急利用で時間を短縮できます。 |
| JR 大阪駅 | JR大阪環状線 → JR天王寺駅 → JR大和路線 (奈良駅経由) → JR桜井線 (天理行き) | 約1時間20分 | 乗り換え回数が少ないルートです。 |
| JR 奈良駅 | JR桜井線(万葉まほろば線) | 約15分 | 桜井線は本数が少ないため、事前に時刻表をご確認ください。 |
最後までお読み頂きありがとうございます。